1. 序文
最近、天の父母様聖会独生女教団において『韓民族選民大叙事詩–独生女の誕生の為に備えられた韓民族』(2024)が、一つの宗教教理的歴史叙述として提起されている。この叙事詩は清州韓氏を古代韓国史の始原として位置づけ、その起源を箕子(きし)の末裔である「韓氏朝鮮」に求めようとする。特に王符の『潜夫論』、李圭景(イ・ギュギョン)の『五洲衍文長箋散稿』、李丙燾(イ・ビョンド)の『韓国古代史研究』などから引用した文章を根拠として、古代朝鮮が正に韓氏の国家であったという主張を展開する。
本稿では、去る2024年に韓国と日本の天の父母様聖会所属の公職者たちを清平に召集して教育した「UPF巡回教育『韓民族選民大叙事詩』講義PPT(2024.11.12)の 177~179頁、そして『韓民族選民大叙事詩』23-27頁について批判的に検討したい。これらの資料では、古代朝鮮が箕子の子孫である清州韓氏によって建国された「韓氏朝鮮」であったという主張と併せて、衛満朝鮮によって滅亡し海中へ移動したという叙事が展開される。
このような叙事は、宗教的信念に基づいて構成された「選民の歴史」という内的正当性を主張しながら、これを通じて六千年ぶりに初めて降臨した独生女としての韓鶴子総裁の血統と使命を歴史的に正当化しようとする目的を内包している。そのため歴史的叙事と呼ぶことさえも恥ずかしく、文献に基づく歴史批評を行う価値すら有していないが、歴史に専門性を持たない独生女教団の信徒を欺瞞しているので、歴史的事実性とその主張の妥当性を文献研究に基づいて批判する。
こうした主張の妥当性は、文献史料に対する精密な分析を通じて検討されなければならない。本稿は該当諸史料を文献批評の観点から再検討し、『韓民族選民大叙事詩』が展開する「韓侯国と韓氏朝鮮」中心の古代史の叙述が実証史学の観点から受容可能なものか否かを分析する。
2.『潜夫論』における韓侯国の記述に関する文献批判(全ジングク2011)
『潜夫論』は後漢末期の王符(AD.90年頃活動)が著した政治・倫理書であり、その中の「志氏姓」篇において以下のように記述している。
「昔周宣王 亦有韓侯, 其國也近燕……其後韓西亦姓韓, 爲衛滿所伐, 遷居海中。」
(王符 n.d./再引用:全ジングク 2011)
(訳:「昔、周の宣王の時代にも韓侯がおり、その国は燕に近かった。……その後、韓西もまた韓の姓を名乗ったが、衛満に征伐され海中に移された。」)
この文章は、周の宣王の時代に「韓侯」という諸侯が存在し、その国は燕国の近くに位置し、後に衛満に滅ぼされて「海中」へ移されたという叙事を提示している。『韓民族選民大叙事詩』はこの一節を根拠に、韓半島の古代に既に韓氏の政権が存在し、衛満朝鮮以前の古代朝鮮が正に「韓氏朝鮮」であったと主張するが、しかし、次のような批判が可能である。
第一に、『潜夫論』は紀元2世紀頃の記録であり、古朝鮮滅亡(紀元前108年)からは約200年が経過した時期の著作である。即ち衛満朝鮮の実在と活動に関する一次史料ではなく、後世の思惟と文学的想像力が加味されている可能性が高い。
第二に、ここでいう「韓侯」は実在の人物ではなく、『詩経』の「大雅・韓奕」篇に登場する象徴的な諸侯国の「韓侯」に基づいた後世の人々の想像と見られる。既に西周時代の諸侯国としての「韓」は、韓半島とは地理的にも文化的にも明確に区別される存在であった。
第三に、「韓西」が韓半島の特定地域を意味するという解釈も、文献に基づかない推測に過ぎない。寧ろ「韓の西方」という表現は、中国北西部の国境地帯にあった辺境国家として解釈されるべきであり、これを古朝鮮と直接結びつけるのは無理な飛躍である(全ジングク2011)。
以下は『詩経』の「大雅・韓奕」篇の一部である(黄ウィドン1956):
奕奕梁山、維禹甸之。(煌びやかな梁山は大禹が開拓した郷である。)
有倬其道、韓侯受命。(その都は広大にして、韓侯は天命を受けた。)
韓侯出祖、出祖侯度。(韓侯は祖先に従い進み、祖先は侯の道を歩んだ。)
……………………………………………
溥彼韓城、燕師所完。(広大なるあの韓城は燕の軍師が完成したという。)…
この詩は、韓侯が天命を受け北方の蛮族(貊)を征伐して北国を統治し、周の王室から諸侯の地位を与えられたのを詠じた内容である。しかしこの韓侯は、後代の東夷族の韓と直接関連する存在というよりは、西周時代(BC.1046~771)の燕国近郊の諸侯として象徴的な人物に近い。
この詩が古代史研究者たちの注目を集める理由は、清州韓氏や「韓」の名称に関連している故ではなく、春秋時代(BC.770~403年)の初期から中期に当たる西周時代の燕国(南燕)が戦国時代(BC.403~221年)の七雄の一つであった燕国(北燕)とは異なる地域にあったという部分の故である。つまり戦国時代の燕は現在の河北省の北京一帯にあったが、春秋時代初期の燕は中国黄河以南にあったという根拠を示す文献という点で学界の研究対象となっている(全ジングク 2011)。
3.『五洲衍文長箋散稿』の韓氏朝鮮の記述に対する検討
実学者の李圭景(イ・ギュギョン1788~?)は『五洲衍文長箋散稿』において次のように記述した:「箕子朝鮮は新たな支配勢力として登場した韓氏朝鮮である。」
この文は「箕子朝鮮」と「韓氏朝鮮」を同一視し、古朝鮮の初期の支配勢力が箕氏ではなく韓氏であったという主張を内包している。この主張は、李圭景が朝鮮王朝時代後期の儒学者として箕子崇拝思想を伝統的な儒教的名分論と結びつけて再構成した一種の歴史認識に過ぎず、実証的な古代史記録に基づいているわけではない。
『韓民族選民大叙事詩』はこの文に基づいて、箕子朝鮮を統治した韓氏が正に清州韓氏の先祖であり、衛満に追われて「海中」へ移されたという『潜夫論』の叙事と結びつけて「韓氏朝鮮」の系譜を構成するが、しかしこれは朝鮮王朝時代後期の事大主義的儒教認識と少数姓氏の家門神話を連結した虚構的系譜構成に過ぎない(金テユン2010)。
4. 李丙燾の「韓氏朝鮮」論に対する批判
李丙燾(イ・ビョンド)は『韓国古代史研究』において「新支配氏族は箕氏ではなく韓氏であった」と記述し、古朝鮮の継承者としての韓氏の優位性を主張した(1992)。これは朝鮮後期の一部の族譜(例:『清州韓氏世譜』)に登場する「箕子→準王→馬韓→韓氏」という系譜を実証史学的に受容した代表的な事例である。
しかし李丙燾の他の著作では『三国志』や『後漢書』などに基づき箕子朝鮮の実在性そのものに疑問を呈しており、彼もまた箕子を「歴史的実在人物」として認めるよりも伝説的存在と見なす傾向を示していた(1992)。したがって彼の「韓氏朝鮮」論は、実証史学者としての李丙燾の一貫した歴史認識から逸脱した政治的または文化的配慮として解釈される余地がある。
李丙燾は日本植民地時代の植民地史観の提唱者であった津田左右吉と今西龍の影響を強く受けた人物と評価される。この両者は古朝鮮の実在性と檀君神話を否定し、これを神話または伝説の範疇として解釈したが、李丙燾は彼らの学説を受け入れ、檀君朝鮮は実存国家ではなく神話的構成体に過ぎないと見なし、古朝鮮は衛満朝鮮において初めて実証可能な実体として登場すると見た。したがって彼の古代史叙述は「檀君は虚構であり衛満は歴史」という植民地史学的な構図の中で展開され、彼が言う「韓氏朝鮮」もまたそのような構図の中で「箕子朝鮮」を再解釈した一種の正統継承論であり文化的翻案と評価することができる(李丙燾1935年;今西龍1970年; 津田左右吉1924年; 愼鏞廈(シン・ヨンハ)1998年)。
5.結語
『韓民族選民大叙事詩』は、清州韓氏の起源を古代の「韓氏朝鮮」に置くことによって、韓国古代史の始原を特定姓氏中心の宗教的叙事へと再編しようとする。本稿ではそのような主張に対して『潜夫論』の韓侯国記述、李圭景の『五洲衍文長箋散稿』に見られる韓氏朝鮮認識、そして李丙燾の「韓氏朝鮮論」を中心に文献批判を行った。
まず『潜夫論』に登場する韓侯は燕国近郊の西周時代の諸侯国であり、古朝鮮あるいは箕子朝鮮と地理的・文化的に関連性が立証されていない象徴的人物に過ぎない。これを衛満朝鮮と結びつけ「海中」移住叙事へと拡張するのは、実証的史料に基づかない誇張された解釈である(全ジングク 2011)。
『五洲衍文長箋散稿』において李圭景が提示した「箕子朝鮮=韓氏朝鮮」の同一視も儒教的名分論と姓氏神話を結合した観念的叙述に過ぎず、歴史学的に証明された命題ではない(全ジングク2011)。
また李丙燾は「韓氏朝鮮」の優位を主張しながらも、他の著作では檀君朝鮮と箕子朝鮮双方の実在性に懐疑的な立場を堅持した。これは彼の学問的一貫性から逸脱した二重的な叙述であり、植民史観の論理を借用して古朝鮮を排除して箕子及び衛満朝鮮以降の歴史を「実体のある国家」として認めようとする構造の中で形成されたものである(全ジングク2011)。
このような歴史叙述は、17世紀以降の族譜刊行の文脈においても確認される。『清州韓氏世譜』は箕子の後孫として韓氏家系を設定しているが、実際には始祖の韓蘭と箕子との直接的な系譜を立証できないままに、後世に構成された名分的な系譜に過ぎない。これは後世の家門神話が如何に宗教的信念と結合し歴史叙事へと変容するかを示す代表的事例である(高ソンベ2023)。
結局、『韓民族選民大叙事詩』は歴史叙述ではなく、宗教的神話を正当化する為の叙事的装置に過ぎない。特に古代史に関する未検証の引用と推論を通じて特定の姓氏と宗教指導者の血統を「選民的」に構成しようとする試みは、学問的厳正さは勿論、一般信者に対する知識的欺瞞という点で批判されるべきである。このような叙事は古代史の実体を明らかにしようとする歴史学の目的とは全く無関係であり、寧ろその歪曲である。
後続論文である『韓民族選民大叙事詩』批判-3では、この叙事体で主張する天神、神女、天孫降臨神話に対する歪曲された意味解釈を批判してみたいと思う。これらの神話は本来、天の子孫(天孫)が地上に降臨して女性を選択し、その間に生まれた子孫が新たな国を建てるという建国神話の構造を持つ。これは古代東アジアの建国神話や聖書及び原理講論で語られる「メシヤ降臨」神話と類似した構造を成している。それにも関わらず『韓民族選民大叙事詩』はこれを韓鶴子独生女の家門神話と結びつけ、フェミニズム的な独生女神話として再解釈し、本来の意味を歪曲している。このような神話の変造は宗教的イデオロギーを裏付ける為の意図的な装置であり、歴史的・神話的意味の本質を毀損するものであるが、これに対する批判的考察を後続論文によって進めていく。
参考文献
高ソンベ「韓国族譜博物館所蔵『清州韓氏世譜』の刊行体制と特徴に関する研究」
『書誌学研究』94、2023
高ソンベ『清州韓氏世譜刊行に関する研究』忠南大学校大学院 2023
金テユン「朝鮮時代後期の清州韓氏族譜から見た箕子と箕子朝鮮の認識」中央大学大学院2010
王符『潜夫論』(年度不明) 再引用: 全ジングク(2011)『韓の起源と形成』
韓国学中央研究院
愼鏞廈『日帝植民地近代化論批判』文学と知性社1998
李圭景『五洲衍文長箋散稿』(年度不詳) 韓国学中央研究院蔵書閣所蔵書籍
李丙燾「三韓問題の新考察」『震檀学報』2号、3号、1935
『韓国古代史研究』朴英社1992
全ジングク『韓の起源と形成』 韓国学中央研究院2011
鄭ビョンソル(訳注)『訳注 詩経集伝 下』伝統文化研究会 2009
鄭ウンリョン「楽浪関連墓誌銘に見られる箕子継承意識」『韓国史学報』65、2016
黄ウィドン「詩経の解釈」『東国史学』第4号、東国大学校史学会 1956
今西龍 「箕子朝鮮伝説考」 『朝鮮古史の硏究』 国書刊行会 1970
津田左右吉 『神代史の研究』 岩波書店 1924
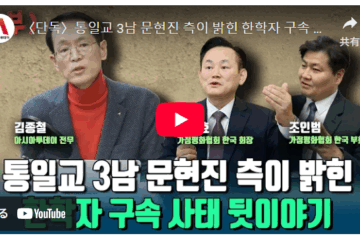
0件のコメント